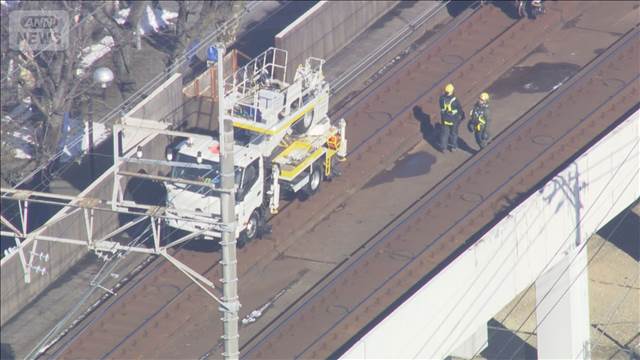名古屋大学・岡山大学などの共同研究チームは、植物が細胞の分裂方向をそろえる仕組み(制御機構)を解明したと発表しました。
2025年9月13日にアメリカの科学誌「CurrentBiology」に掲載された論文によりますと、研究チームは、ゼニゴケとシロイヌナズナを使って、細胞分裂の際に現れる「CORD遺伝子」の働きを解析しました。
その結果、「CORD遺伝子」が産生するタンパク質が、細胞分裂に不可欠な「紡錘体」と呼ばれる構造の「向き」を安定させ、正しい方向に細胞分裂できるよう制御していることを突き止めました。
通常、細胞分裂では、「紡錘体」が染色体を2つに分けて、均等に配置します。
動物細胞では(細胞分裂の極性を決める)「中心体」と呼ばれる構造がこの紡錘体の方向を決めますが、一方で、植物細胞にはほとんどの細胞に「中心体」がないため、紡錘体の向きを決める仕組みは長らく分かっていませんでした。
今回の研究で、正常なゼニゴケの細胞分裂の過程においては、微小管の束である「プロスピンドル」と呼ばれる構造がつくられ、これらを軸に紡錘体が形成されるのに対し、CORD遺伝子を破壊したゼニゴケでは、紡錘体の向きが乱れることが分かりました。
研究の成果について、研究チームは「中心体を持たない植物細胞の分裂方向を制御する仕組みが明らかになった。動物細胞とは異なる進化の道筋をたどった植物ならではの仕組みであり、植物が水中から陸上に進出した道筋の理解に手掛かりを与えるもの」としています。