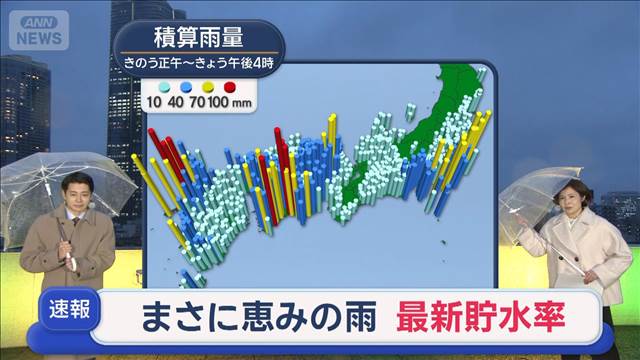視聴者の皆さんの疑問に答える「みんなのハテナ」。今回のテーマは夜空に輝く「月」です。10月6日の月曜日は「中秋の名月」です。
10月6日は中秋の名月。中秋の名月とは旧暦の8月15日に見える月のことで、1年で最もきれいに月が見える日だと言われています。
そんな月にまつわる最初の疑問は……
月はいつできた?(高松市 HARU 48歳)
地球ができたのは約46億年前と言われています。
教えてくれたのは、星が美しく見える町として知られる井原市美星町の美星天文台の綾仁一哉台長です。
(美星天文台/綾仁一哉 台長)
「地球も太陽の周りを回っているかけらみたいなものがどんどん集まって大きなかたまりになるという形でできてきた、それと一緒に月もそういう感じでできたという説があったり、たまたまどこかから飛んできたのが地球に捕まってぐるぐる回っているという説もあったりしたがどれも一長一短だった」
月の誕生には、地球が高速で回転した結果、一部が月となった分裂説や、地球の引力によって太陽系を移動していた月を引っ張ってきた捕獲説など、さまざまな説がありました。
しかしアポロ計画で行われた調査や実験などで、地球と月の非常に似ていることなどが分かり、現在最も有力な説は巨大衝突説です。
(美星天文台/綾仁一哉 台長)
「できて間もないころの地球に、火星ぐらいの大きさの地球の半分くらいの天体がぶつかった、ぶつかって破片ができてそれが地球の周りを回っているうちにその破片がどんどん集まって月になった」
巨大衝突説が有力となり、月ができたのは地球ができた1億年後の約45億年前と言われています。
しかし地球や月の地形にそのような衝突のあとが確認されていないなど、まだまだ謎は多いということです。
月の裏側は?(笠岡市 コマキチ 41歳)
(美星天文台/綾仁一哉 台長)
「月に飛んで行った探査機がもう月の裏側の写真も撮っている。月って結構表側と裏側でだいぶ様子が違うみたいで、私たちは表側のうさぎの形を見ているけど、そういうのは月の裏側にはほとんどない」
私たちが地球から見る月は月の公転と自転がほぼ同じスピードなため、いつ・どこから見ても表側が見えています。
月の裏側には私たちが「うさぎ」などに例える黒い陰、「海」と呼ばれるものがほとんどないのが特徴です。
「海」は、現在は終息している月の火山活動によって約35億年~40億年ほど前にできたと言われています。
(美星天文台/綾仁一哉 台長)
「昔、月の地下から溶岩・マグマがしみ出してきて、溶岩の海ができて冷えて固まったもの。ただその黒いところが裏側にはほとんどないことがわかっていて、どうしてそういう違いがでているのかはいまだに謎」
月に人は住める?(総社市 キノリ 42歳)
(美星天文台/綾仁一哉 台長)
「まあ……将来そういったことは可能かなと思う。まずは基地を作らないといけない。月の表面に空気はないので」
綾仁さんによると、人が住める環境を月に整えられさえすれば住むことは可能だということです。しかし現実的にはなかなか難しそうです。
(美星天文台/綾仁一哉 台長)
「月の表面は非常に環境が厳しい。(表面温度が)-170℃ぐらいになったりもする。それにも耐えられるような施設でないといけない」
月には大気がないため地球と同じように気温で測れませんが、月の表面温度は昼間で110℃ぐらいまで上がり、夜になれば-170℃ほどまで下がるそうです。
それ以外にも、呼吸はどうするのか、水や食料はどうするのかなど人が住むための問題は多そうです。
日本で中秋の名月をめでる習慣ができたのは、中国から伝わってきた平安時代ごろです。
中秋の名月がきれいなのは、他の季節と比べて空気が澄んでいることや月の見える高さが見やすい位置にあることなどが理由です。
ときには月を眺めてもの思いにふけってみてはいかがでしょうか?
(美星天文台/綾仁一哉 台長)
「表面のデコボコを見るのが何度見てもおもしろい。あとは月の明るさを全身で受け止めていただいて、もうお好きな方法で楽しんでいただけたらと思います」
6日は中秋の名月ですが、実は満月となるのはその翌日の7日です。実際の月の満ち欠けの周期と旧暦が完全に一致していないためだということです。
中秋の名月と満月が重なるのは、次は5年後の2030年だということです。
(2025年10月2日放送「News Park KSB」より)