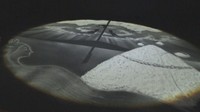気象庁の有識者検討会は、富士山などの火山が大規模な噴火をした際の情報発信について「火山灰警報」を新たに導入するなどの提案を盛り込んだ報告書を公表しました。
火山の大規模な噴火に伴い、大量の火山灰が降る事態への対策を巡っては今年3月に国が住民の避難行動を「ステージ」ごとに分類し、降灰量が30センチ以下なら原則として在宅での避難を継続するという基本方針を取りまとめました。
そうした方針も踏まえて、気象庁は大規模な噴火が起きた際に発表する情報の見直しを有識者検討会で進めてきました。
25日に公表された報告書では、火山灰による重大な災害が起きる恐れが高まったことを伝える「火山灰警報」の新設が提案されました。
国が基本方針で示した住民の避難行動の分類に対応する形で、降灰量の累積が0.1ミリ以上3センチ未満の場合は「注意報」、3センチ以上30センチ未満の場合は「警報」、30センチ以上の場合は雨が降ると木造家屋が倒壊する恐れがあるため「一段強い呼びかけ」を発表するとしています。
また報告書では、気象庁がこれまで運用してきた「火山灰予測情報」は1ミリ以上の降灰を同一のカテゴリーで扱っているため、大量の火山灰が降る事態に対応できないと指摘し、火山灰が降る量の見通しを6時間先まで数センチ単位で細かく伝える改善案も盛り込まれました。
気象庁は今後、数年をかけて関係自治体との協議や必要な技術開発などを行い、報告書で示された提案を実現する方針です。