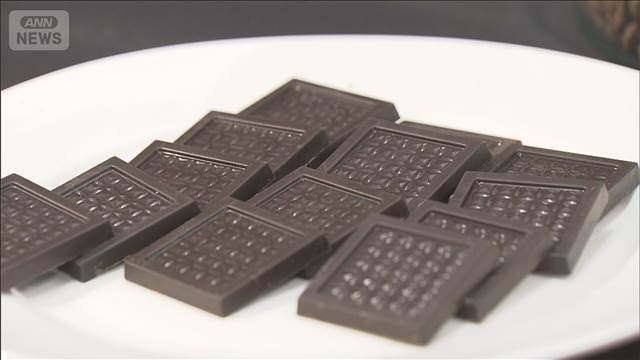生きた化石ともいわれる「カブトガニ」。カブトガニの保護に取り組んでいる岡山県笠岡市が25日、「復活に手応えを感じている」として会見を開きました。
(笠岡市教育委員会/大重義法 教育長)
「ここ数年で大きく増加をしてきております。大きな期待感をもって受け止めています」
笠岡市によりますと、2024年度に笠岡近海では漁業者の網にかかるなど75匹のカブトガニが捕獲されました。前年度の約2.5倍で、市の記録によると76匹が捕獲された1989年度に次ぐ数となっています。
かつて笠岡の海には多くのカブトガニが生息していましたが、1970年代の大規模な干拓で繁殖や成長に必要な砂浜や干潟が少なくなり、激減しました。
笠岡市立カブトガニ博物館では漁業者に捕獲されたカブトガニに卵を産ませ、ふ化した幼生を育てて翌年7月頃に放流しています。一度も脱皮していない幼生は捕食されるなどのリスクが高いため、一度脱皮した後に放流しています。カブトガニはふ化した後、十数年かけて成体になるとされています。
笠岡市では、捕獲数が増えた要因として、2014年前後に大量に放流した幼生が順調に育っていることや、そのころ砂浜で多くの卵が観察されていたことなどを挙げました。
(笠岡市/栗尾典子 市長)
「笠岡には本当に豊かな自然がありますので、その自然を自分たちの自慢となるように、カブトガニがシンボルである」