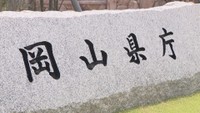農林水産省は2020年時点の推計で、近くにスーパーやコンビニなどがなく、車も使えず買い物が困難な高齢者が岡山県に17万人いるとしています。地方自治に詳しい専門家は、団塊の世代が後期高齢者になり状況はさらに厳しくなると話します。
(みんなの集落研究所/石原達也 代表)
「現実としては今、80代、90代の方々を70代、60代の息子さん・娘さんが週末とかに通って、買い物をお手伝いするケースが多いと思う。息子さん・娘さん世代がまさしく団塊の世代で、2025年には(75歳以上の)後期高齢者になりますので、5年・10年していくとより大変になるのでは」
こうした状況を受け、自治体は買い物が困難な人が出ないようバスを運行するなどしています。また、過疎地の買い物ニーズに着目した企業が、移動販売車を走らせ食料品を売るなどしています。
そんな中、住民自らが困難を解決しようという動きがあり、注目を集めています。
住民主体で店舗と移動販売
「高齢化」が進み買い物に行くことが難しい人、いわゆる「買い物弱者」への対応が課題となる中、岡山県北部の中山間地域での取り組みが注目を集めています。住民が主体となり困難な状況を打開しようというものです。
岡山県勝央町にある「どんどん市場」です。手作りのお弁当やおかず、地域でとれた野菜などを販売しています。
2019年にオープンしたこの店。地域住民が出資して一般社団法人を立ち上げ、運営しています。きっかけは長年この場所で食品や生活雑貨を販売していた店が無くなったことでした。
(一般社団法人よしの/瀧上勤 代表理事)
「ここがもしなくなったら、生活困るよね。買い物困難者いっぱい出てくるよねということになって……」
店のオープンに当たり町も整備費を支援しました。
「どんどん市場」がある吉野地区と、となりの古吉野地区には、合わせて約1000世帯が暮らしています。町の中でも比較的高齢化が進んでいます。
どんどん市場では週に5日、買い物に来るのが難しい人に移動販売車で商品を届けています。5日間で100戸ほどが利用するということです。
(利用者[89歳])
「免許ももう返してしまってな。どこにも行けれんけんな。この人らが来てくれるのを待ちよる」
(利用者[92歳])
「今の大型のお店でも買い物する楽しみも昔はあったんですけど、今は足がもろいですし、広いお店をカートを押して回るのはちょっと難儀になりまして」
移動販売は、高齢者の見守りも兼ね町の非常勤職員である「集落支援員」が担っています。この取り組みは買い物困難者の課題解決につながる事例として2025年2月経済産業省のコンテストで、優秀賞に選ばれました。
(一般社団法人よしの/瀧上勤 代表理事)
「自分たちで盛り上げていかないとどうしようもない。田舎ってそんなところじゃないですか。どんどん右肩下がりになっているような状態なので、右肩下がりにしちゃダメよね。フラットでもいいから、活気のあるところを作り出していきたい」
地元の有志が立ち上げた無人店…きっかけは「中学生の声」
真庭市にある吉地区です。73世帯が暮らし、高齢者の割合が約6割。コンビニやスーパーは、最も近いところで、15km以上離れています。
そんな吉地区に、2023年10月、スマートフォンで買い物をする無人の店「スマートストア」がオープンしました。
(吉縁起村協議会/鈴木昌徳 会長)
「バーコードがありますから、このように写真も写りまして、これで決定すると」
店を立ち上げたのは地元の有志でつくる地域おこしグループ「吉縁起村協議会」です。NTT東日本のグループ会社が全国展開するサービスを使って営業しています。
売っているのは、自ら仕入れた食料品や調味料など。利用者の希望も受け付けています。
山あいの過疎地域にあるスマートストア。オープンのきっかけは、まだ車を運転できない「中学生の声」でした。
(吉縁起村協議会/鈴木昌徳 会長)
「コンビニがほしいって言われたんですよね。コンビニをいろいろ当たってみたんですけど、ちょっと最初の資金がいりますので、どうがいいかなぁという中で、最終的に行き着いたのがスマートストア」
しかし、月の売上げは2万5000円から3万円ほどで、1カ月のシステムの利用料5万5000円にも届きません。
協議会は、赤字が続く吉地区の店舗を維持するため、3月、より多くの利用者が見込める真庭市の市街地3カ所にスマートストアをオープンしました。
(記者リポート)
「真庭市役所のスマートストアには、職員の方が小腹を満たせるようなものやホッと一息つけるような商品がそろっています」
高校の近くの店舗では、文房具を多く取りそろえるなど、店舗ごとに品揃えを変え、協議会は4店舗トータルでの黒字を目指す考えです。
(吉縁起村協議会/鈴木昌徳 会長)
「地域住民の皆さんの福祉向上の役に立てたらいいなと」
協議会にアドバイスなどをしている市の担当者は、この事業について高齢者だけでなく中高生を含めた多くの人の買い物支援につながる可能性があると期待を寄せています。
(真庭市地域振興課/中島一郎さん)
「あらゆる年代の方々の生活の質を高めることによって、このまちに住み続けてもいいかなと、地域の人口を増やすまでは行かないかもしれませんけど、減少を食い止めることができるのではないかと期待しています」
活動メンバーの「高齢化」を懸念
これらの取り組みが、過疎地での買い物の課題を解決することにつながればいいなと思います。
ところで、今回取材した2つの団体は、活動しているメンバーの「高齢化」を懸念していました。今後、活動の担い手の確保も重要になってきそうです。
取材したみんなの集落研究所の石原達也代表は、「買い物の課題解決の取り組みに、より若い世代が仕事として関われる仕組みをつくれば、持続可能な支援につながるのではないか」と話しています。