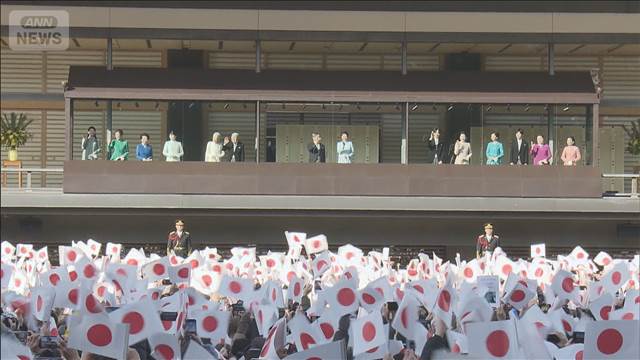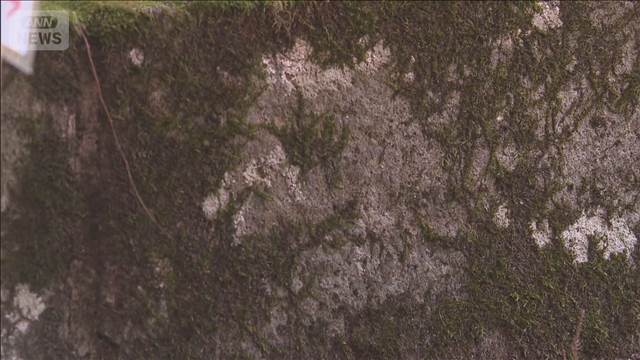岡山大学学術研究院医歯薬学域(医)地域救急・災害医療学講座の小原隆史講師らの研究グループは、新型コロナ禍をきっかけに心肺蘇生の際の「人工呼吸」の実施率が下がり、年間約10人の子どもが、本来助けられたはずの命を失っていた可能性があることが分かったと発表しました。
研究成果は7月5日、オランダの学術雑誌、Resuscitationに掲載されました。
子どもの病院外心停止は、窒息や溺水などが原因になることが多いため、人工呼吸による蘇生が推奨されています。しかし新型コロナ禍により、感染リスクへの懸念から、トレーニングを受けていても人工呼吸を控え、近年は胸骨圧迫のみの蘇生が普及していました。
研究グループは、消防庁のデータを用いて2017年から2021年までに行われた17歳以下への心肺蘇生3352例について解析しました。
その結果、人工呼吸を含む蘇生が行われた割合は、コロナ禍前の33.0%から、コロナ流行期は21.1%に減少していました。
また人工呼吸をせず胸骨圧迫のみの心肺蘇生を行ったケースについて分析すると、30日以内の死亡率と有意に関連があり、特に「呼吸性心停止」のケースで、その傾向が顕著であることが分かりました。
そしてコロナ禍に人工呼吸を控えたことにより、胸骨圧迫のみの心肺蘇生を受けた子どものうち、2年間で21.3人(年間10.7人)が多く死亡した可能性があると推計しました。
研究グループでは「子どもの心停止に対して人工呼吸が極めて重要であることを改めて裏付けた。感染対策を講じた上での安全な人工呼吸法の確立や、人工呼吸用ポケットマスクの普及など、社会全体で取り組むべき課題がある」としています。