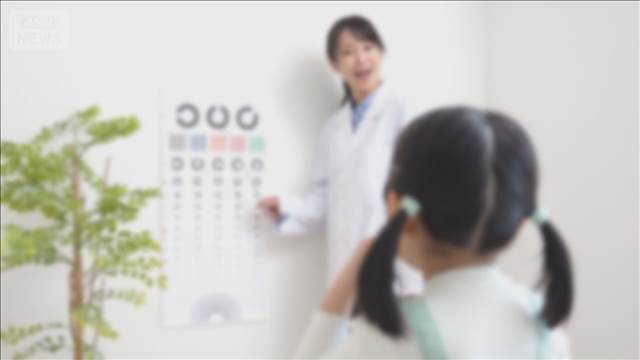桜の季節が終わってもふと足元を見るとたくさんの花が咲いています。岡山市中心部、KSB瀬戸内海放送の岡山本社の周辺で小さな草花を探しました。
サクラが散りすこし寂しい街なか、ふと、足元を見ると道端に、小さな花が咲いています。
ナズナ/アブラナ目アブラナ科
「春の七草」の一つナズナの花。よく見ると白い小さな花が集まって咲きまるで王冠のようです。
ハート型の実が付いた柄をすこし細工してくるくる回すと、かすかに聞こえる音やこの様子を三味線にたとえ、ナズナは別名ぺんぺん草と呼ばれています。昔の子どもたちの素朴な遊びです。
荒れた土地を表すのに「ぺんぺん草も生えない」と言ったりしますが、どんな荒れた土地にも生えるナズナの旺盛な繁殖力からきた言葉です。
スミレの仲間(スミレ科)
用水路沿いに濃紺の美しい花がー。春を代表する花、スミレです。
野山で可憐に咲くイメージがあるかもしれませんが、実は、道路の片隅やコンクリートの割れ目にも生えるたくましい植物。
あっ、こんな所(用水路の壁面に)にも! すみっこ暮らしはお手のものです。
カラスノエンドウ(マメ科)
日当たりが良ければどこにでも生えるカラスノエンドウ。よく茂るため畑や庭では厄介者扱いされがちですが、よく見ると丸みのあるかわいい花。
紫色の穴は花外蜜腺と呼ばれる器官です。蜜でアリを誘っている理由は葉や茎を食べるイモムシなどから、守ってもらうためと考えられています。
キュウリグサ(ムラサキ科)
パステルブルーとイエローの、まるで絵本に出てきそうな愛らしい花。コンクリートの隙間などどこにでも生えていますが、小さいためその美しさは見落とされがち。植物の名前はキュウリグサ、もむとキュウリのようなにおいがするのが名の由来です。
ハハコグサ(キク科)
黄色い帽子をかぶって泥んこあそびをする子どものような姿、ハハコグサです。春の七草の一つで「オギョウ」「ゴギョウ」などとも呼ばれています。
道端にも生える身近な草で、かつては「草もち」の材料にも使われました。
カタバミ(カタバミ科)
黄色い花は、カタバミです。コンクリートの隙間などに根を張り地面にはりつくように生えます。時間帯や気象条件により葉を閉じる、おもしろい特徴があります。
どんな場所にもちゃっかり生える街なかの美しい草花。しゃがんでじっくり眺めると、新たな発見があるかもしれません。