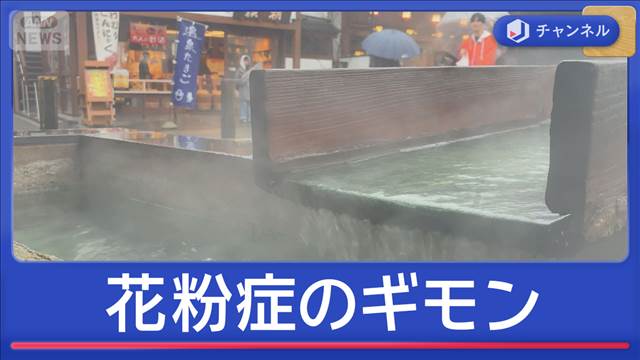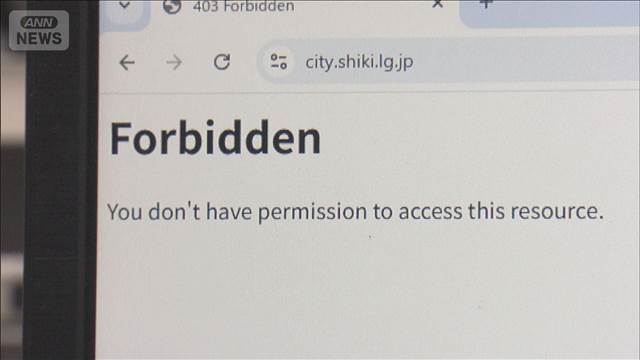Park KSBアプリに寄せられた疑問をもとにお伝えする「みんなのハテナ」です。今回のテーマは「応援」です。
皆さんはいま応援しているものはありますか? 視聴者のみなさんからは「応援って意味があるの?」や「応援の方法の良し悪しは?」などの疑問が寄せられました。みなさんの「応援」に関する疑問にお答えします。
「誰かを元気に!」「何かの励みに!」と自然としてしまう「応援」。声に出したり、祈ったり、やり方は人それぞれ。そこで最初のハテナは……。
「応援っていつから始まった?」(高松市 えびぞうさん 46歳)
教えてくれたのは京都橘大学の総合心理学部の教授で九州大学の名誉教授も務める山口裕幸教授です。
(京都橘大学 総合心理学部/山口裕幸 教授)
「人類40万年20万年とか言われますけど、食料の確保、外敵からの防衛であり、子育てみんなで一緒にやってきた。そういう中で協力し合うことや助け合うことを、それがないと生き延びていけないと学んできている」
山口教授によると応援の始まりの1つとして考えられるのは人類が生きていく中で選び学んできたものだということ。
生きるために助け合ったり子育てをしてきたりした関係から、自己の利益よりも他者の幸福を優先する愛他性や、他者の利益になるような行動をするような向社会性と呼ばれるようなものが生まれ、それが段々と強められたのが「応援」の始まりの1つだということです。
その応援も地域ごとに違い、現代の日本では楽器などに合わせてみんなで声を出す応援が多いのに対し、アメリカなどでは個別に声を出す応援が多いのも、これまで暮らしてきた文化やメンタリティなどが応援スタイルの違いに影響しているとしています。
(京都橘大学 総合心理学部/山口裕幸 教授)
「日本はどちらかというと空気を読む方に、相互協調的である方にちょっと天秤が傾いている、アメリカやヨーロッパはどちらかというと自分の意見を主張することの方に傾いている。バランスの違いが応援スタイルにも現れているとみてもいいと私は思っている」
「応援って効果があるの?」(香川・宇多津町 ヨッシー 36歳)
みなさんは応援の効果、あると思いますか?
(京都橘大学 総合心理学部/山口裕幸 教授)
「社会心理学ではそれなりに実証研究も数多く行われていて、応援っていうのが応援される側の動機づけを高める、パフォーマンスを高める効果があるというのはよく言われている」
山口教授によると、応援によって「自分ならできる」という「自己効力感」が高まることで、パフォーマンスが上がるなどの効果がある程度はあるとのこと。
さらに、応援される側の条件と、する側の仕方などによって応援の効果は少し変わるということです。
(京都橘大学 総合心理学部/山口裕幸 教授)
「初心者の場合にはやはり温かく。失敗しても『頑張れ、気にするな』というような応援の仕方がパフォーマンスを上げるのに効果があるが、プロのような人たちはある程度の緊張感を持って臨んだ方がいいパフォーマンスにつながるので、応援する側もそれなりの厳しい目も持って応援した方がいい」
「どのようにやるのが効果がありますか?」(倉敷市 あーさー 43歳)
応援していた人が失敗した時にどんな声をかけますか?
(京都橘大学 総合心理学部/山口裕幸 教授)
「応援が強い期待を感じさせて、普段はできることもできなくなるということもある、なかなか心理学的にいうと応援の効果は結構デリケートな部分を含んでいると思う」
山口教授によると、そもそも人が応援をする理由は「自分と他人を重ね合わせる、同一視」をして自分の事のように思う心理が働くから。
例えば、子どものピアノの発表会。練習してきた姿を見ていざ本番! 見る方も緊張しますし、うまくできればうれしく思いますよね。
一方で……思うような結果にならない時もありますよね。そういった時にいきすぎた同一視は自身の自己肯定感を傷つけられたように感じ、応援している人を悪くいう事や誹謗中傷などをする人もでてきてしまいます。
(京都橘大学 総合心理学部/山口裕幸 教授)
「ただ一方的に攻撃して自分のフラストレーションを発散しているだけの場合には、批判される側の人は心が動かない、もちろん応援されていると思えない」
山口教授が応援の仕方について大事なポイントの1つに挙げたのが、相手の気持ちを汲み取り自身の感情をぶつけないこと。ときには声を掛けるのが相手にとってネガティブな感情につながる場合もあります。応援される人の立場や置かれている状況をしっかりと考えることが大切だとしています。
(京都橘大学 総合心理学部/山口裕幸 教授)
「自然と応援する気持ちを持っていれば表情や仕草などに表われますので人間は、そういうところで感じ取ってもらうとかも可能だと思う」