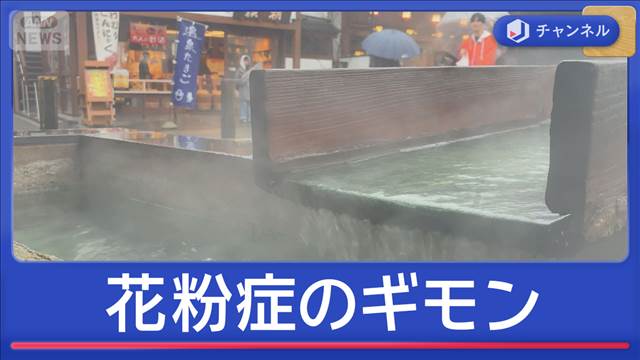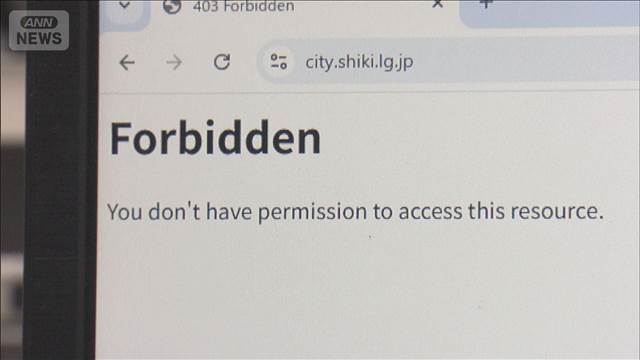Park KSBアプリに寄せられた疑問をもとにお伝えする「みんなのハテナ」です。今回のテーマは「お盆」です。お寺の住職に答えてもらいました。
なぜ「盆」と言うの?由来は?(丸亀市 完熟梅 54歳)
疑問に答えてくれたのは、高松市の高善寺の住職、鎌田拓子さんです。
(高善寺/鎌田拓子 住職)
「お盆というのは元々は仏教用語でいうとこういう字になります。『盂蘭盆(うらぼん)』というのが正式な言い方です。この『盂蘭盆(うらぼん)』という字がどこからきているかというと下にカタカナで書いていますが、インドのサンスクリット語、『ウランバーナ』と言います。この『ウランバーナ』が何かというと、『逆さまにつるされる』という意味なんですよね」
「お盆」は正式に「盂蘭盆」といって、その語源はサンスクリット語で「逆さづり」を意味する「ウランバーナ」といわれています。
なぜ「逆さづり」かというと、仏教の言い伝えではお釈迦様の弟子・目連が仏教の死後の世界のひとつ「餓鬼道」に落ちた母を救うために多くの僧と一緒に供養したとあります。
「餓鬼道」に落ちると逆さにつるされることから、逆さづりを意味する「ウランバーナ」が「盂蘭盆」、そして「お盆」へと変わって、先祖供養の行事として定着したそうなんです。※諸説あります。
日本のお盆は古くは旧暦の7月15日を中心とした3日間でした。現代ではほとんどの地域では新暦の8月15日を中心とした3~4日間となっていますが、一部地域ではそのまま7月に行っているところもあるそうです。
お盆にお供えするものは?(善通寺市 とら 58歳)
(高善寺/鎌田拓子 住職)
「その地元でとれる農産物でいいかなと思います。高松ならうどんとか素麺、自分たちのソウルフードですね。岡山ならブドウ、モモ、ナシそれらがベストかなと。私なんかは自分の好きなお菓子を置いてお供えして、それを(あとで)いただいております」
お供えは、供えた後は仏様のお下がりとしていただくのが前提となっていて、魚などの傷みやすいものなどは避けた方がよいそうです。
なぜ灯ろうを飾る?使い回しは?(倉敷市 大将 76歳)
お盆を間近に控えた仏具店は「盆灯ろう」や「切子灯ろう」などが販売の最盛期を迎えています。
「盆灯ろう」は霊が迷わずに家に帰り着くように、「切子灯ろう」は無事にお墓に戻れるように飾ります。仏具店によると、仏壇の両側に左右一対で置く「盆灯ろう」は毎年、使い回しても構わないそうです。
これに対して仏壇の横に天井からつり下げる「一日灯ろう」は初盆から3年間だけ1年ごとに買い換えます。
色は初盆は白色、2年目は銀色、3年目は金色と変えていき、4年目以降は飾らないそうです。地域によってデザインも変わるということです。
お盆の法要は家でしかできないの?(高松市 ラック 51歳)
(街の人は―)
「(お盆は)実家からかなり離れているのでなかなか……」
「(お盆の行事は)家ではしないんですけど、おばあちゃんちに行くとやります」
親戚一同が集まって毎年行っていたお盆の法要も状況が変わっているようです。高松市の葬祭場で聞きました。
(ベルモニー葬祭 高松/横山春子さん)
「やはり、コロナの時代をはさんでしまったからだと思います。コロナの時代に人に声を掛けにくくなった、呼ばなくなったというところが大きく原因を発しているのではないか」
新型コロナや住宅事情の変化によって実家などで行うことが減ったお盆の法要を斎場で行えるのでしょうか?
(ベルモニー葬祭 高松/横山春子さん)
「はい、可能です。広い畳の間があっても皆さん正座をするのが難しい方が増えてきましたから、会館で椅子を使って駐車場もたくさんあるので、安心して行っていただけるようになっています」
お盆期間はどんなことをするのか。高善寺の鎌田住職に聞きました。
(高善寺/鎌田拓子 住職)
「自分が自分の命を喜びながら生きていくということがご先祖様に対しての一番の供養になるのではないかと思う。もちろんお墓参りも大事ですが、私たち自身の日々の生活をもう一度見つめ直していただく、そういう機会になれば幸いです」