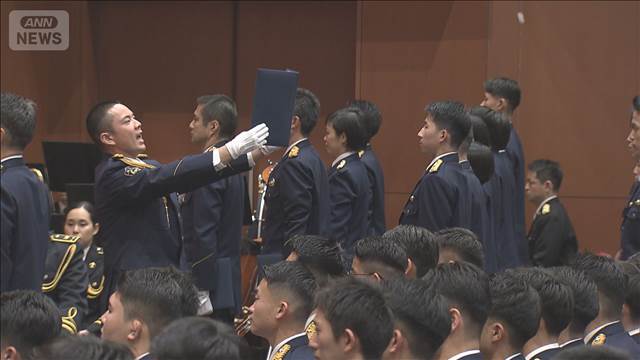社会課題を解決するアイデアを、プログラミングしたレゴブロックで表現し、プレゼンする大会があります。岡山市の小学生チームがこの国内の大会を通過し、国際大会に挑みます。デジタル技術とチームワークを生かして、世界にアイデアを発信します。
動いているのは、プログラミングされたレゴブロック。全体で飛行機や船の事故が多い海域『バミューダトライアングル』を表していて、事故を減らすためのさまざまなアイデアをブロックを使って表現しています。
社会課題を解決するアイデアを、プログラミングしたレゴブロックで表現してプレゼンする「FIRST LEGO League」という大会に向けたものです。
作ったのは、小学2年生から5年生までのチーム、「WHITESTAR」の4人。
メンバーは、チームのリーダーで4年生の岡田百々花さん。モデル設計を主に担当している5年生の山本匠真さん。プログラミングが得意な5年生の吉武豊さん。チーム最年少ながらイラストなどでプレゼンを彩る2年生の長岡星那さんです。
同じロボットプログラミング教室に通う4人。別々の小学校に通っていますが、好奇心旺盛でとても仲良しです。大会に向けてチームを組み、プレゼンに取り組んでいます。
「事故の多い海域で事故を減らす」というテーマを自分たちで決めて、温かい海で起こるハリケーンの発達を防ぐため、海をかきまぜて海面の温度を下げたり、事故の原因となる海底のメタンガスを海に出さないよう貯めてエネルギー源とするなど、実在する研究を参考に独創的なアイデアを生みだし、表現しました。
(小学4年生/岡田百々花さん)
「メタンガスが大量発生すると船は浮力を失って沈没します。そこで、空気のドームを海底のメタンガスが発生する場所につくって、 超音波消泡装置で泡を消すことで船の沈没を防ぎます」
(小学5年生/山本匠真さん)
「ハリケーンの発生源と思われるプエルトリコに限定してバブルネットを設置しました。すると海面の温度が下がり、ハリケーンが発生しにくくなります」
4人はこのアイデアをプレゼンし、2024年12月の地域大会、2025年2月の全国大会で高い評価を受けました。
(小学2年生/長岡星那さん)
「(全国大会の時は)1年生だったけど、発表を頑張った」
そして、8月にマカオで開かれ、世界30カ国から500チーム、1万2000人が参加する国際大会に出場します。
この日もブロックやプレゼンをブラッシュアップしました。みんなで一緒に、たくさん考えます。
(小学5年生/吉武豊さん)
「みんなで議論しているからこそ、このいいものができたと思っています」
アイデアを基にブロックを組み立てますが、頭の中では思いついているものの、形にするのは難しいようです。
また、ブロックがどんな動作を何秒間するかなど、アプリを使いプログラムします。
(小学5年生/吉武豊さん)
「このライトをオンにしてから次にメッセージ1、別のメッセージを送ります。そしたらこのモーターが5秒間動きます」
(小学4年生/岡田百々花さん)
「プログラミングは自分で1から考えるので、もしできなかったら、どんどんもっといい方法はないかなって確かめるところが楽しい」
いいプレゼンのためにはパネル作りも重要です。パネルに貼るイラストを準備中。生成AI「ChatGPT」で思い通りのイラストになるよう挑戦しています。
日本語でプレゼンしていた全国大会までと異なり、国際大会では英語で伝えなければなりません。
プログラミングにパネル作りにプレゼン。デジタルの枠を飛び越え、さまざまな力が問われる大会で、4人で力を合わせて、世界に自由なアイデアを発信します。
(Crefus北長瀬校/増田将 先生)
「問題解決力、自分で課題を見つけてそれを解決するにはどうしたらいいんだろうっていう、常に自分で問題を見つけていく力は必ず付いていく。楽しみながらやってくれているのが一番いいかな」
(小学5年生/山本匠真さん)
「せっかく途中まで頑張ってきたことだし、せっかくここまで来たんなら一か八かで楽しむことが目的」