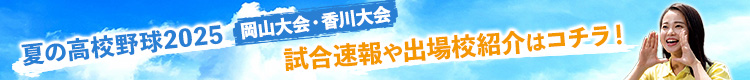ケロリンと書かれた黄色い桶(おけ)。銭湯などで一度は目にしたことがあるのではないだろうか。解熱鎮痛薬のケロリンが誕生して、今年で100年。なぜ黄色い桶が全国に広がったのか取材した。
■「ケロリン桶」最初は黄色ではなかった?
銭湯に通う人たちにとってなじみ深い「ケロリン桶」。皆さんは、この桶がどのように全国に広がったのかご存じだろうか?
桶を製造・販売しているのは富山めぐみ製薬。
富山めぐみ製薬 笹山敬輔社長 「ケロリンはいわゆる配置薬という富山の薬で、家庭の薬箱に入っている薬から始まったのが、戦後になって薬局薬店にも置いてもらうという活動を始めた時に、宣伝にすごく力を入れまして」
大正14年、解熱鎮痛薬「ケロリン」が誕生した。今年は昭和100年でもあり、ケロリン100周年でもあるのだ。
昭和33年には、ケロリンのCMソングを制作し、ラジオなどで流した。しかし、広告費の高さなどで社内からは批判の声が。その時、ある広告代理店からこんな提案があったという。
広告代理店 「銭湯の桶に広告を載せませんか?」
昭和38年ケロリン桶が誕生。この桶を全国の銭湯に安く販売することでケロリンの宣伝をしたのだ。
実は、製造されて1年間は黄色ではなかった。日本銭湯文化協会の町田忍理事に話を聞いた。
「昭和38年登場した時は、この白だったんですけどね。白は汚れが目立つというので、すぐ黄色に変わりました」
昭和39年の東京オリンピックを控えた日本は、さまざまな物が木製からプラスチックへと移行している時期でもあり、プラスチックの桶が珍しかった。
町田理事 「(銭湯で)一番使われるものは、まさに桶。銭湯のケロリン桶は、まさにシンボル的なもの」
■現在も全盛期と同じ個数製造
今ではケロリン桶は黄色だが、当時1年ほどしか製造されなかった白のケロリン桶を、去年まで使っていた銭湯が東京・足立区にあると聞き、番組は早速向かってみた。
玉の湯 店主 堀田晃一氏 「こちらになります。いわゆる『白ケロリン』」
およそ60年、白のケロリン桶が活躍した玉の湯。現在は展示されているが、触ったり写真が撮れるサービスをしている。
「(Q.見た人のリアクション)変わったバージョンとか、こんなのがあるんだとか、新しいのがあるんだというような勘違いをされる人が多いです」
全国の銭湯で使用された「ケロリン桶」だが、銭湯は昭和43年をピークに減少。それに伴い、桶の製造量も伸び悩んだ。
ところが平成になったころ、東急ハンズからケロリン桶の販売オファーが舞い込んだ。
笹山社長 「こんな宣伝が入ったものが売れるわけがないんじゃないかという」
ところがこれが大ヒット。さらに、アニメキャラクター「ケロロ軍曹」とのコラボが実現し、大きく売り上げを伸ばした。
現在もケロリン桶は全盛期と同じ年間で4万~5万個製造され、日本国民に愛されている。
笹山社長 「子どもが銭湯の絵だったり温泉の絵だったりを描く時に、桶を黄色に塗るんですよね。本当は何色でもいいはずなのに、桶は黄色に塗るというのを見ると(ケロリン桶が)浸透してるなと実感します」
■黄色い桶が2種類? 違いの理由は
62年前に誕生したケロリンの黄色い桶だが、実は2種類あることをご存じだろうか。
微妙に直径や深さに違いがあるのが分かるだろうか。直径は左側が22.5センチに対して、右側は21センチ。高さは左側が11.5センチに対して右側は10センチと、右側の桶のほうがやや小ぶりになっている。 なぜ微妙にサイズが違う2種類の桶が作られたのか。
左側の桶は「関東版」。右側の少し小ぶりの桶は「関西版」。
なぜ関西版の桶が小ぶりなのかというと、関西では銭湯などの湯船からかけ湯をする文化があり、扱いやすいように少し小さくしたのだそうだ。重さは関西版は関東版に比べ、100グラム軽くなっている。
これまでに250万個、販売されたケロリンの桶だが、関連グッズも人気だという。
バスタオルやサウナハットなどのお風呂関連だけでなく、マグカップやキーホルダーも人気だそうだ。
製薬会社の公式サイトのほか、アマゾンなどの通販サイトで購入することができる。
富山めぐみ製薬の代表取締役社長・笹山さんは「長い時間をかけて、全国の銭湯や温泉にケロリンの桶を広めてきたことで、日本の銭湯文化として根付いたと思います。今後、さまざまなコラボ商品を企画しているが、世界進出できるようなコラボができれば」と話していた。
(「大下容子ワイド!スクランブル」2025年7月15日放送分より)