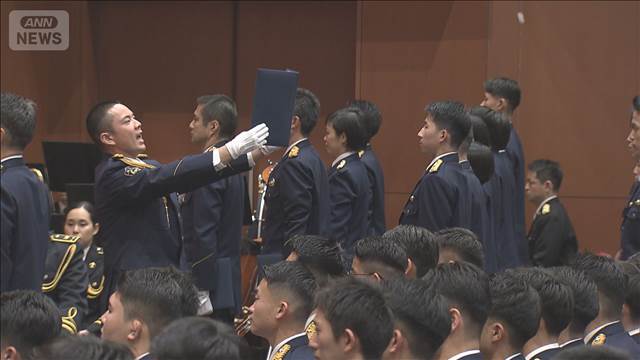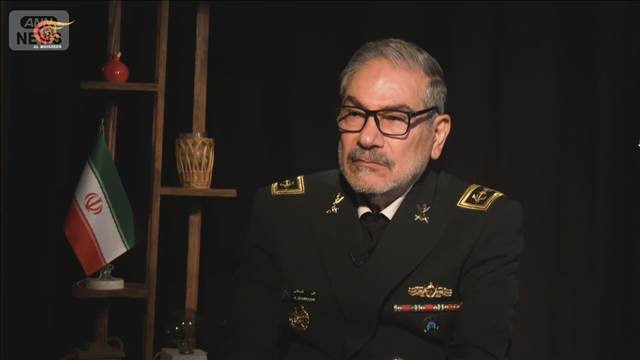香川県丸亀市に、ある身近なものをマイクロプラスチックの回収に生かす研究をしている小学生がいます。その研究成果は、県の発表会で最優秀賞を受賞するなど、高く評価されました。
丸亀市の小学6年生、塚本怜子さん(12)。
塚本さんは、直径5mm以下の海ごみ「マイクロプラスチック」をあるものを使って回収する研究をしています。
その「あるもの」とは……
(塚本怜子さん)
「消しカスでマイクロプラスチックを集めました」
消しゴムのカス!? 一体どういう事なのでしょうか。
研究内容を塚本さんが実際に海岸で教えてくれることに。塚本さん、早速マイクロプラスチックを見つけると、なにかを取り出します。
(塚本怜子さん)
「これが細長さんといって、練り消しを細長くして、ひもで結んでくっつけている装置。これをここにこうやって置いて、ここにプラスチックが付く」
約4時間装置を置くことで、消しカスと海ごみがくっついて一体化するそうです。これは、消しゴムに含まれる成分がプラスチックに触れることで溶け出すという性質を利用したもの。
塚本さんがこの性質に着目したきっかけは、部屋を掃除していた時でした。
(塚本怜子さん)
「小学校低学年の時に使っていた筆箱(の内側)に消しカスがくっついていたんですね、そのまま。『これ(ごみ集めに)いいんじゃない?』と思ってやりました」
海岸の清掃活動を通して海ごみに以前から興味があった塚本さん。筆箱の中で溶けていた消しカスがヒントとなり、夏休みの自由研究で「消しカスを使ったマイクロプラスチック回収」をテーマに調べました。
(塚本怜子さん)
「これはどの消しゴムに一番プラスチックがくっつくかという実験をした際のものです」
研究では、薄く切った5種類の消しゴムに、プラスチックを付けて放置し、どの消しゴムが一番くっつくかを調査。
また、大量に消しカスを作り、束や編状などにして、くっつきやすい形も調べるなど研究は続きました。
ちなみに、作った装置にそれぞれ名前を付けるなど、楽しみながら研究した塚本さん。ただ、研究自体はかなり大変だったそうです。
(塚本怜子さん)
「(消しカス集めは)ひたすら手作業。手が痛かった。夏休みでいけるかなと思っていたら全然いかなくて、9月半ばくらいまではやった」
研究成果をまとめた後、担任の推薦で丸亀市の児童科学体験発表会・高学年の部に出場。
その結果、市の発表会を突破し、香川県の発表会では最優秀賞に輝きました。
(塚本怜子さん)
「最初はうれしかったのもあるんですけど、ビックリしたのが大きかったです。いけたらいいなという感じだったので、本当にいけるとは思っていなかった」
発表会ではプレゼンテーションも行われるということで、理科の先生がアドバイスをしたそうです。
(宮花昂平 先生)
「話し方などをアドバイスしました。すごい練習をたくさんしてくれていて、練習の度に成長を感じました」
助けてくれた存在はほかにも。塚本さんが研究で一番苦労したという消しカス集めを手伝ってくれたのは同級生でした。
(同級生は―)
「とにかくれいちゃん(塚本さん)が優勝してほしいという気持ちで進んで行動しました」
「これからも頑張って一つに向かってやりたいことを頑張って研究してほしい」
友達からもらった消しカスをまだ大事に持っている塚本さん。感謝の気持ちを胸に、研究を続けていきます。
(塚本怜子さん)
「いっぱい集まったので「タコ足タコさん」みたいな(大きな)機械を作れたらなと。この実験が間接的にでも世界のごみ問題を減らしていくのに役立てばなと思います」