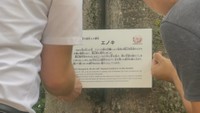戦後80年を迎え、戦争の実体験を語り継ぐ人が減っています。戦争を知らない世代が今後どう伝えていくのかを考えます。
(岡山県遺族連盟/増本信行 事務局長)
「ちょっと切れ端なんでね。これが軍服に敵機の銃撃を受けて貫通した、穴が開いたシャツの一部ですね」
戦没者の遺族などでつくる岡山県遺族連盟が2020年に開館した「岡山平和祈念館」です。
(松木梨菜リポート)
「約500人の遺族の方から寄せられた、軍服ですとか手紙、遺品など800点が展示されています」
体験伝える取り組みを強化
戦後80年を迎え、遺族連盟は戦争体験を伝える取り組みを強化しています。
(岡山県遺族連盟/増本信行 事務局長)
「戦没者遺族を二度と出さないという原点に立って、戦争の悲惨さを身をもって体験した人でないと語れない部分を伝えていけたらと考えています」
戦争で家族を亡くした人に「語り部」として活動してもらおうと遺族にアンケートを配布。聞き取った戦争体験などをまとめ、活動に使う資料を作っています。
こうした作業は増本さんが1人でしています。このほかにも……
(岡山県遺族連盟/増本信行 事務局長)
「きょう届きました。200本納入していただきました」
思いを広く伝えるため、遺族連盟として初めて映像を制作しました。
(岡山県遺族連盟/増本信行 事務局長)
「若い世代の人に戦争の悲惨さを知ってほしいということで。県の教育委員会や市町村の教育委員会に送らせていただきたいと思っています」
語り部の高齢化が課題
2025年度、小・中学生に平和について伝える活動を2024年度より増やしたいとしていますが、語り部の高齢化で思うようにいかないのが現状です。
遺族連盟の会員はこの40年で半数以下に減り1万4000世帯に。ほとんどが80代となりました。孫世代の50代、60代でつくる青年部もありますが、その数は100人。実際に活動している人は少ないといいます。
(岡山県遺族連盟/増本信行 事務局長)
「孫世代から下になりますと、どうしても現役世代ということでお仕事が忙しかったりするということで。どう継承していくかは経験のないことですので、孫世代、ひ孫世代の方が遺族会活動に加わってつなげていかないといけないと思っています」
戦後80年…国も語り部の活動に力を入れる 補助金は2024年度の4倍に
戦争で家族を亡くした遺族でつくる全国組織の日本遺族会に、厚生労働省は2024年度、語り部活動の活動費に補助金を出しています。
2024年度は2500万円を補助し、全国で講話を500回開いてほしいとしていました。
さらに戦後80年となる2025年度は、活動を強化してもらおうと2024年度の4倍の1億円を補助。目標として全国で講話を1500回開くよう求めています。
2025年度、日本遺族会は各都道府県に150万円ずつ配分していて、岡山県遺族連盟もこの補助金でDVDを制作したり今後、語り部活動の研修会を開いたりする予定です。
戦争を知らない世代が語り継ぐ時代へ
国も語り部の活動に力を入れる中で、岡山市では戦争を知らない世代が平和のバトンをつなごうとしています。
7月、平和の大切さを考える会に参加した山陽学園中学校・高校の生徒8人です。被爆体験の朗読などをしました。
(参加者)
「親世代の私たちも語り継ぐことを頑張っていきたいと思いました」
生徒らは8月、広島市を訪れ、20都道府県の中高生らが参加した「全国こども平和サミット」で語り部活動などについて発表しました。
(山陽学園中学校・高校/緒方康之 教諭)
「主催側の方から参加してもらえませんかと声がかかるようになった。地道な活動が認められてきてるのかなと」
8月7日、生徒らは広島での活動を振り返りました。
(山陽学園中学/山田紗季さん[3年])
「私たちやこれからの世代がもう戦争をしないように私たちが語り継いでいきたいなと」
今後「若い世代」がバトンをつなぐことについて提案も。
(山陽学園高校/武元悠真さん[3年])
「調べたりするときとかにGoogleとかじゃなくて、TikTok使ったりして、いまに合った必要な伝え方をしていかないといけないなと」
今後、被爆体験の朗読や紙芝居をSNSでも発信することになりました。
(山陽学園中学校・高校/緒方康之 教諭)
「TikTokやInstagram、個人的にはワクワクするような意見が出たので生徒たちと有志を募ってまたやってみたいと思っています」
(山陽学園高校/武元悠真さん[3年])
「50代とか40代の人口が多い世代の方も取り込めれば活動の規模が大きくなるのかなと思いました」
(山陽学園中学/山田紗季さん[3年])
「日本は比較的平和で戦争に参加してないと思うんですけど、戦争を経験して反対してきた方々がいたからこその状況だと思うので、私たちがそれを担ってやっていきたいと思っています」
専門家「身近なところから始めることが大切」
戦争を知らない世代が語り継ぐ時代へ。戦争が残す記憶を研究する岡山大学大学院の中尾准教授は、身近なところから語り部を始めることが大切だと話します。
(岡山大学大学院/中尾知代 准教授)
「おじいさん、おばあさんがちょっとしたときにああだったよとか、こういう戦地にいたんだとか、そういうことを少しでも語っていらっしゃる家庭は意外と多いと思うんです。そういうファミリーヒストリーの側面も大事じゃないかと思います」
その上で記憶の継承を図ってほしいと訴えます。
(岡山大学大学院/中尾知代 准教授)
「このごろこういうiPhoneがありますので、身近なところの戦争の記憶を語り継ぐ。そういうものをこれからインターネットのウェブサイトにアクセスして聞くっていうやり方も広がっていくんじゃないかなと思います」
総務省が発表した2月現在の人口推計によりますと、戦後に生まれた人は人口の9割となりました。戦争の体験を今あるデジタル技術などで語り継ぐことが求められます。渡されたバトンをつなぐため、今できることを考えたいと感じました。