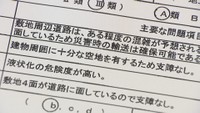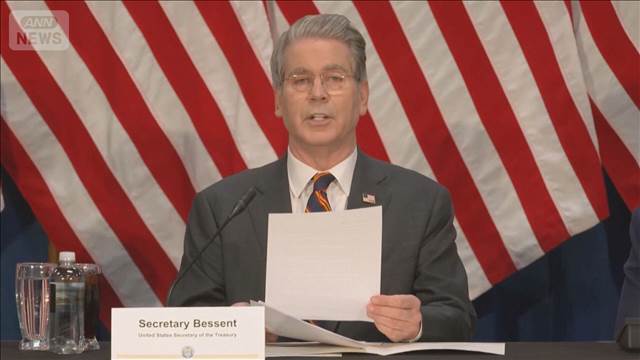建築家・丹下健三が設計した旧香川県立体育館の解体に向けた手続きが進んでいます。民間から公費を使わない再生の提案がある中、県は「安全の確保を急ぐ必要がある」と説明していますが、取材を通じ、その「根拠」が揺らいでいます。
旧香川県立体育館の解体工事の業者を決める一般競争入札は9月5日に開札され、1社以上の応札がありました。今後、審査を経て落札業者が決まります。
2025年7月、建築家らが設立した「旧香川県立体育館再生委員会」が民間の資金でホテルなどに再生することを提案していましたが、県は解体のスケジュールを変えませんでした。
(香川県/池田豊人 知事[8日の会見])
「地震時の倒壊や崩壊の危険性がある旧県立体育館については、そのリスクをなくすことが最も重要なことであると考えております」
知事の定例記者会見では、4週連続で旧県立体育館についての質疑が中心になりました。
知事の発言をまとめると、倒壊の危険の「根拠」となったのは、2012年、丹下都市建築設計(現TANGE建築都市設計)に委託して行った耐震診断の結果です。
その後、耐震改修工事の入札不調を経て、閉館。約7年間、事実上の「塩漬け」状態が続いた後、2021年度に民間に利活用の意向を聞く調査を行い、2023年2月に解体の方針を決めました。
この間、現在に至るまで約13年、新たに耐震性についての調査は行っておらず、解体決定時、理由に挙げたのは災害時の緊急輸送路に指定されている旧体育館の前面道路への影響でした。
しかし、KSBが情報公開請求で入手した耐震診断の報告書をみると、「災害時の輸送確保は可能」とされていたことが判明。
9月1日の会見で知事に問うと……。
(香川県/池田豊人 知事[1日の会見])
「一番は、建物自身が倒壊するのではないかという、ここが最大のポイントでございます」
これまで議会の答弁や会見で強調してきた緊急輸送路への影響については県が独自に判断したもので、倒壊に伴う「付随的なもの」だと述べました。
では、本当にがれきが道をふさぐほどの倒壊は起こり得るのか? 旧県立体育館を設計した丹下健三氏の長男、憲孝さんが会長を務める「TANGE建築都市設計」に取材したところ、「地震によって建物にどのような被害・損害が生じるかについては耐震診断書で具体的な言及はしていない」という回答が返ってきました。
丹下都市建築設計の診断は、構造耐震指標(Is値)と保有水平耐力に係る指標(q)を「数値」で示したもの。
この数値を、国土交通省の耐震診断の基本方針についての告示に当てはめると、「地震の震動、衝撃に対して倒壊、または崩壊する危険性がある」となります。
これは「危険性が高い」に次ぐ3段階中2番目の分類で、県はこれをもって倒壊の危険について説明していたことが分かりました。
記者「具体的な壊れ方についてはいつ、どのタイミングで、誰が判断したんでしょうか?」
(香川県/池田豊人 知事)
「あれだけのものが倒れて倒壊、崩壊ということでございます。一般的なことを想定をしておりますけれど……その状況ということについては、そういった判断の中での、私もそうですし、教育委員会のほうの表現だと思います」
記者「解体の方針を決める中でこの2012年の耐震診断をいわば後付けの論理として利用したんじゃないかとも感じたんですが」
(香川県/池田豊人 知事)
「それは全くございません」
「旧香川県立体育館再生委員会」は解体工事に関わる公金の支出差し止めを求める「住民監査請求」を行いました(郵送で8日付で監査委員事務局が受理)。
民間による代替案の検討が行われていないことや、建物の安全性に関する県の判断が具体的、客観的な裏付けを欠いていることなどを挙げ、解体工事費の支出は違法、不当だと主張しています。