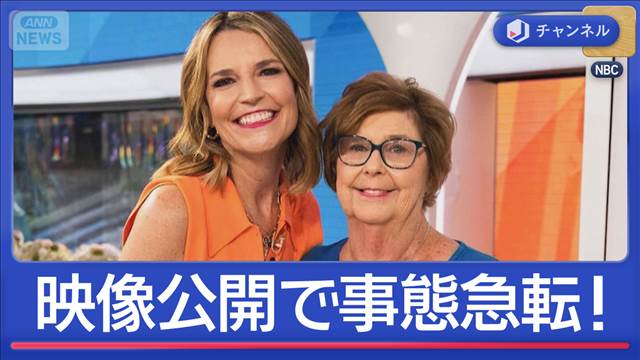暮らしに密着した経済の話題を取り上げる「暮らし×経済」です。今回のテーマは衣食住の一つ、「衣服」です。
季節が影響?購入の動きは
季節が秋になり、皆さんは秋服などを買っているのでしょうか。
(3児の父親)
「買う月があったりなかったりすると思うんで、季節に1回買う感じです。今物価高の上昇で食費の方にお金かかってきてるんで。おもちゃも高くなったのかな。お洋服にかかるお金は減ってきていると思います」
(学生)
「学生なので学費もあり生活費もありでかつかつなので買ってないです」
(3児の母親)
「ユニクロ、GUとか、メルカリで買っています。ほかの方が使ったのを。ほかが上がってるんであんまり節約した分をどこかに回しているという意識はないですけど、食材が上がってるんで」
街では買う頻度が減ったと答える人が多い中、販売店は?
(岡山髙島屋MD本部/森健太 次長)
「この秋に入ってからは、9月、10月は5%ぐらいは(売り上げが)厳しい」
売り上げが厳しい要因には店側の予測も関係しています。
(松木梨菜リポート)
「もう11月ですけれども、売り場を見てみますとダウンなどの厚手のコートはまだ並んでいないようです」
(岡山髙島屋MD本部/森健太 次長)
「去年が暑かったので今年も多分こうだろうと、ものづくりは半年前から進めて各メーカーさんいらっしゃるのでそこが今年は当たらなかったというか。急に寒くなったのが各ブランド苦戦している要因の一つかなと思います」
購入額はバブル期の半分に
秋服購入への動きは鈍かったようですが、そもそも衣類の購入額が「半分に減少した」というデータがあります。
総務省が公表する「家計調査」にある「被服および履物」の支出に関するデータです。1人当たりの購入額は1991年のバブル期は1カ月6671円でしたが、2024年は3336円と、バブル期と比べて半減しています。
減少の背景について専門家は「物価高騰による節約」以外に「SNSの存在」をあげています。
消費行動に詳しい専門家は、衣服の購入額が減った要因についてファッション業界の変化をあげます。
(ニッセイ基礎研究所/久我尚子 上席研究員)
「ファストファッションが2000年代に入って台頭してきた。あとはフリマアプリを使う方が増えましたので、良質な中古品が流通するようになって、積極的に選ぶ消費者が増えてきたことも大きな影響を与えていると思います」
専門家「体験にお金を使う傾向」
さらにSNSによる自己表現の変化も要因とします。
(ニッセイ基礎研究所/久我尚子 上席研究員)
「以前は自己表現が『このブランドのファッションを着ている自分』があったと思うんですけど、今は自己表現が推し活とかイベントとかライブへの参加をはじめとした体験にお金を使う傾向が強まっています」
久我さんが2025年6月に首都圏に住む20代の男女約300人を対象に行ったアンケート調査によると、6割以上が推し活の経験があり、そのうちの約3割が月に1万円以上を使っているということです。
(ニッセイ基礎研究所/久我尚子 上席研究員)
「楽しめる環境が広がっていることによってモノにお金を費やすというよりも、体験にお金を費やすように消費行動がモノからコトへ、モノからサービスへうつっていると考えています」
久我さんによると、総務省の家計調査を分析するとレジャーや旅行など生活を彩るものにお金を使う傾向が高く、食費などの日常の出費を抑える傾向にあるそうです。しばらくはこうした「メリハリ消費」が続きそうです。
(2025年11月5日放送「News Park KSB」より)