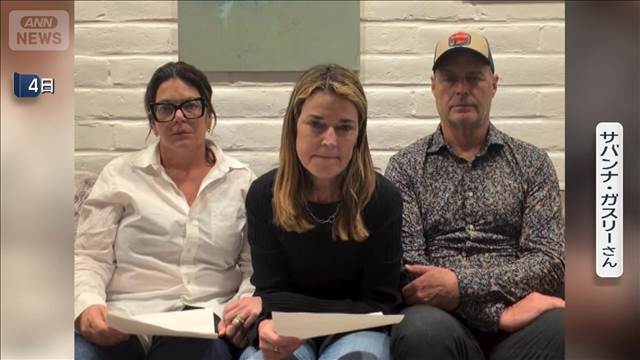視聴者のみなさんの疑問に答える「みんなのハテナ」です。今回のテーマは、色鮮やかなお菓子「おいり」です。
質問に答えてくれるのは、江戸時代後期に創業し、明治以降、代々お菓子を製造・販売している香川県三豊市高瀬町の山下おいり本舗7代目の山地一弘さんです。
おいりとは何?(倉敷市 ちぃ 51歳)他
(山下おいり本舗/山地一弘さん)
「おいりは、1cmぐらいの玉状のお菓子で香川県にしかないお菓子です。おめでたい時の引き菓子として主に(香川県の)西讃地方で結婚式などで用いられます」
おいりは香川県にしかないんです。知っていましたか?
約半世紀ほど前の写真です。三豊市で婚礼の時にお嫁さんが持ってきた「おいり」を、近所の人が白い紙の袋に入れて持ち帰っています。この風習の始まりは約430年前、安土桃山時代までさかのぼります。
讃岐の国の領主、生駒親正公の姫公の嫁入りが決まった時、領内の農家がお祝いに五色の煎りもののあられを献上したことに由来するという説があります。
それ以来、婚儀ではおめでたい「お煎(い)りもの」として広く一般に知れ渡り、嫁入りの「入る」と火で「煎る」とをかけて「おいり」と呼ばれるようになったそうです。
ちなみにお菓子に添えられる小判の形をしたお菓子は夫婦を表しているそうです。
どうやって作る?(高松市 カレー星人 42歳)他
まず、餅米を一晩水に浸し、蒸し上がったら砂糖を混ぜて石臼に入れて杵でつきます。この餅に米糠をふり、熱いうちに麺棒で手早く平らに延ばします。うどんの生地を延ばす要領ですね。
長さ約3mの生地ができると、これをすぐさま屋外の網に広げて乾燥させます。瀬戸内の天日にさらす時間は、季節や天候によって変わります。
(山下おいり本舗/山地一弘さん)
「これが延ばした生地をさいの目に切ってさらに乾燥させたものです」
いよいよ煎っていきます。一分もたたないうちに、四角い生地は丸くふくらみ、真っ白な“真珠”に大変身します。
(山下おいり本舗/山地一弘さん)
「煎りすぎるとちょっと茶色くなってしまいますし、煎るのが足らないとへこんでしまう。きちんとした丸にならないので、そこらへんの加減が勘なので日々悪戦苦闘しています」
(記者リポート)
「煎りたてのおいりです。ほんのり温かく、甘い香りと香ばしい香りもしますが…いただきます。すっと口の中で溶けてやさしい味ですね」
そして味付け色付けして乾いたら、かれんなお菓子のできあがりです。
(山下おいり本舗/山地一弘さん)
「薄いので、おいりが割れないように気を付けて色をかけています」
山下おいり本舗の彩りは七色。サクラが咲くころは「ピンク」「白」「緑」、アジサイが咲くころは「青」「紫」「緑」、木々が紅葉するころなら「赤」「黄」「緑」と、香川の移ろいゆく季節に応じてその色合いを調整しながら提供しているそうです。
(山下おいり本舗/山地一弘さん)
「お嫁さんと地域の結び付きのために発生したお菓子のようなものです。昔は箱詰め作業などでもお店がするのではなくて大きな箱のまま持ち帰って、地域の人が集まって皆で助け合って箱詰め作業をおこなって皆に配っていた。結婚式で使われることがかなり少なくなってきましたので、主に香川県のお菓子として県外の人に喜んでもらえるようなお土産などの形をとって販売しています。手にした人が驚いたり喜びを感じられる幸せのお菓子としてできるだけ長く続けていきたい」