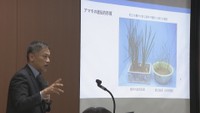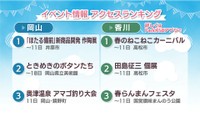岡山大学学術研究院先鋭研究領域(異分野基礎科学研究所)のラ・ラカ・ローマン助教(特任)らは、海洋の環境維持に重要な役割を果たしている単細胞藻類の「ハプト藻」の光合成に関するエネルギー伝達機構を解明したと発表しました。研究成果は5月5日、イギリスの学術雑誌・ネイチャーコミュニケーションズのオンライン版に掲載されました。
ハプト藻類は、地球上の炭素固定の10%、海洋の炭酸カルシウム生成の50%を担う重要な藻類。光合成における光エネルギーの吸収や伝達のメカニズムについて、多くが解明されていません。
研究グループは、光エネルギーを化学エネルギーに変えるタンパク質複合体を、高性能のクライオ電子顕微鏡で分析しました。そして光を集める1個のタンパク質の結合に柔軟性があり、光エネルギーの量に応じてエネルギーを伝達したり余ったエネルギーを逃がしたりする「ハブ」の役割を担っている可能性があることなどが分かったということです。
海藻や海草などは光合成を行い海水に溶けているCO2を吸収しています。その後、海底や深海に蓄積される炭素のことを「ブルーカーボン」と呼び、温暖化対策の新しい選択肢として世界的に注目が集まるようになりました。環境省によると、2022年度の日本における海草や海藻によるCO2の吸収量は年間約35万トンと算定されています。
今回の成果について研究グループは「人工光合成システムの開発にも重要な知見を提供すると期待される」としています。