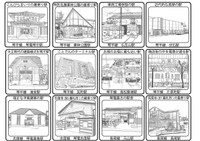南海トラフ巨大地震への対策の検証や被害想定の見直しを進めてきた国の検討会は、死者は最大で29万人を超えるとする新たな被害想定を含む報告書を公表しました。
南海トラフ巨大地震の被害想定を巡っては、2012年から2013年にかけて国の検討会が最悪のケースを試算し、死者は約32万3000人、建物の全壊はおよそ238万6000棟、経済損失は約214兆円に上ると公表しました。
被害想定の公表から10年近くが経過したため、国は2023年に新たな検討会を立ち上げ、これまで取り組んできた対策の進捗状況を検証し、最新の科学的な知見も踏まえて被害想定の見直しを進めてきました。
今月31日に公表された新たな被害想定では、最悪のケースで死者は約29万8000人と推計され、前回の想定から2万5000人ほど減少しました。
また、建物の全壊はおよそ235万棟と推計され、これも前回から3万6000棟ほど減少しました。
津波避難ビルが増加したことや建物の耐震化が進んだことで、前回から死者や建物の全壊が減少した地域があったということです。
名古屋大学 福和伸夫名誉教授 「(国民の方々には)そろそろ本気になって対策を進めてほしい。対策をすれば被害が減るという達成感も国民の方々に持ってもらえる仕組みを作りたい」
一方で、最新の地形データを用いて津波による浸水地域を再計算したところ、福島県から沖縄県の広い範囲にかけて深さ30センチ以上の浸水地域が3割増加したため、前回よりも被害が大きくなると推計された地域もあったということです。
経済損失については約270兆円と推計され、前回から56兆円ほど増加しました。
物価高の影響により復旧・復興にかかる費用の増加が主な要因だということです。
また、過去の南海トラフ地震では時間差をおいてマグニチュード8クラスの地震が発生した事例があることから、今回、初めて時間差をおいて発生する地震の被害想定も公表しました。
先に起きた「先発地震」による建物の損傷が修繕されないうちにその後の大きな地震「後発地震」が起きると、単独で地震が発生するより建物の全壊が約3万1000棟増加するとしています。
一方、先発地震によって津波からの避難意識が向上した状況で後発地震が起きると、単独で地震が発生するより死者は5万3000人ほど減少するとしています。
それに加え、事前避難をしていた場合は死者はさらに1万2000人ほど減少するということです。
また、今回は災害関連死についても初めて被害想定を公表し、東日本大震災や能登半島地震の実績に基づくと、最大でおよそ2万6000人から5万2000人と推計されるとしています。
こうした被害想定を踏まえ、報告書では南海トラフ地震の被害の甚大さや広域性を考慮すると、従来の行政主体による対策だけでは限界があると指摘しています。
そのうえで、行政や事業者によるライフラインやインフラの強靭(きょうじん)化に加えて、国民一人ひとりが「自らの命は自らが守る」という意識のもと住宅の耐震化や家庭での備蓄、さらには迅速な避難行動に取り組むことで「被害は軽減できる」としています。
国は今後、今回の報告書に基づいて防災政策などを定める「防災対策推進基本計画」の改訂に着手する方針です。