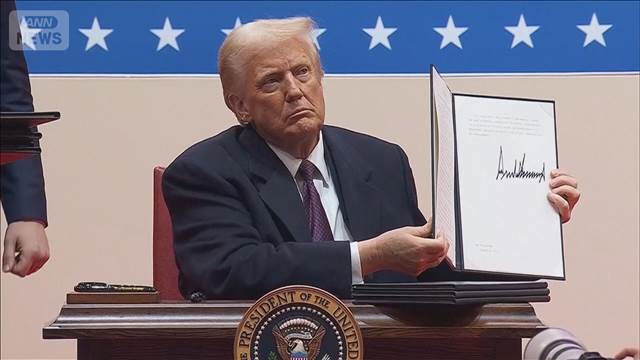9月は「防災月間」です。さぬき市の小学校で災害時にどう行動すべきかを考える授業が開かれました。
(香川大学/金田義行 特任教授)
「震度っていくつからいくつまであるか。0から7まであります」
児童の防災意識を高めてもらおうと、さぬき市のさぬき北小学校で開かれた防災授業です。
地震学が専門の香川大学の金田特任教授が地震の怖さを伝えました。
(香川大学/金田義行 特任教授)
「津波っていうのは、第1波が約1時間から1時間半後に来てそれから何波も来る」
津波はたとえ30cmでも流されることを伝えました。
南海トラフ地震は今後30年以内に80%の確率で起こるとされていて、香川県でも最大で震度7の揺れがくると想定されていることなど、災害に対する備えの大切さを伝えました。
(松木梨菜リポート)
「子どもたちは住んでいる地区ごとに分かれて、災害時に自分たちの周りで何が起こりそうか、地図を見ながら考えています」
津波が来やすい場所や土砂が崩れそうな場所を見つけ地図に貼っていきました。
最後は災害時にとるべき行動を発表。
(児童の発表)
「周りに建物や木がない場所に逃げる」
学区内で気を付けるポイントを共有しました。その時……。
(放送)
「避難指示が発令されました。3階の各教室に避難しなさい」
避難訓練がいきなりスタート。告知なしの訓練でしたが、全員が落ち着いて行動し終了しました。
(児童は―)
「冷静に行動することが大事だと思いました」
「いろんな危険な場所を知れて気を付けようと思いました」
「備えと進めていきたいと思います」
(香川大学/金田義行 特任教授)
「自分たちの地域を理解した上でどう対応するかを子どもさんたちが自ら考えるのは大事で、地震がいつ起こってもきちんと対応できる心構えが必要と思います」