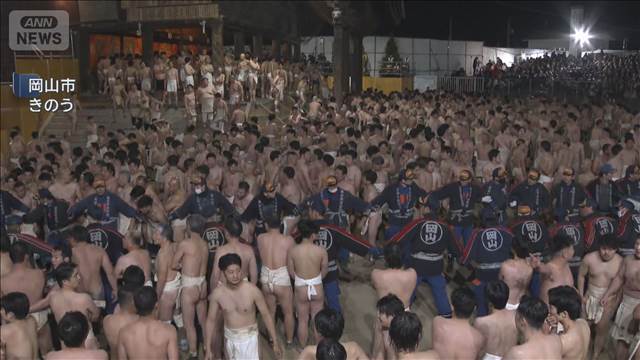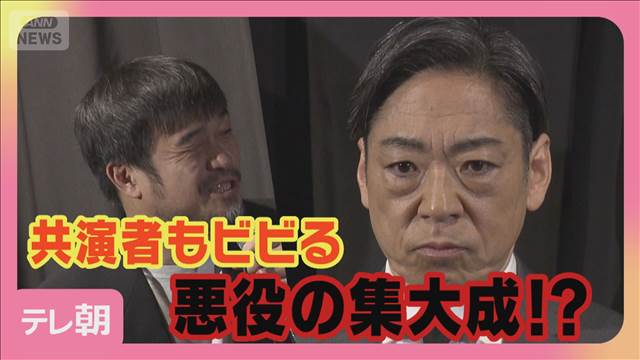瀬戸内国際芸術祭の秋会期が10月3日に開幕します。秋から会場に加わる香川県三豊市の粟島には、アーティストと島の人が一緒に作り上げた作品がお目見えします。
三豊市の須田港から船で15分の粟島。旧中学校を活用したアート施設「粟島芸術家村」で、6月からアーティストの夫婦が滞在制作に励んできました。
この場所のアートの特徴が、島の人たちによる「全力のサポート」です。
草花の顔料など、島の自然を生かした作品
かつての教室では、東京都出身のアーティスト柏木崇吾さんが、島の自然を生かした作品を展開。
島の人たちに粟島のお気に入りの草花や野菜などを持ち寄ってもらい、顔料を抽出して絵を描きました。
(東京都出身/柏木崇吾さん)
「島にあって違う形をしていたものを抽出して、自分の体を通して違う色や形に変換されて表現として定着するところが面白みを感じている」
(野口真菜リポート)
「私も粟島のツバキの葉を摘んで色を煮出してもらいました。これで粟島のお気に入りの景色などを描きます」
(野口真菜リポート)
「完成しました! 粟島の夕陽スポット・西浜で、大好きな島のおじいちゃんと一緒に夕陽を見た日の思い出です」
さらに柏木さんは、島の4歳の女の子の手で型を取った作品も制作。未来を照らす子どものパワーで植物が成長する様子を訪れるたびに目の当たりにできます。
船乗りたちの思い出を追体験
柏木さんの妻で、中国内モンゴル自治区出身のタオリグ・サリナさんが作り出すのは、粟島の元船乗りたちの思い出を追体験できるインスタレーションです。
粟島には1897年に日本最古の海員養成学校が作られ、多くの船乗りが世界の海へと漕ぎ出しました。
サリナさんは島の人たちと一緒に、船乗りの思い出を象徴する100羽ものカモメを作ったり、会場となる旧体育館を片付けたりと準備を重ね、モンゴル高原に住む遊牧民の移動式住居「ゲル」の作品を設置しました。200本以上の木材を使った、高さ3mを超える巨大な作品です。
(中国内モンゴル自治区出身/タオリグ・サリナさん)
「毎日来てくださる島のおばあちゃんたちがいて、平均年齢が80歳くらい。午前中は畑をやって午後はこっち来て一緒に作業して、お茶とかして話をするのが好きなので、いつも笑いながら話をしているのが、制作もいい雰囲気になって私も気楽にできたのがすごい楽しかったです」
そして、90歳を超える島の元船乗りなどから当時の思い出を聞きます。
大海原を航海した船乗りと、大草原でゲルで暮らす遊牧民。「移動しながら暮らしを紡ぐ」という共通点が、幻想的な空間の中で描き出されます。
作品づくりを支えた島の人たち
そんな2人を支えてきた島の人たちは、粟島のアート活動に欠かせない存在です。
2010年に香川県の事業として始まった「粟島芸術家村」は、東京藝術大学学長の日比野克彦さんを総合ディレクターに迎え、三豊市が独自に継続。15年にわたってほぼ毎年、国内外のアーティストを招いてきました。
歴代の作品は今も島の人が保管・展示していて、瀬戸芸がない年も毎週土曜日に一般公開しています。
(島民ボランティア/松田悦子さん)
「若い人とお年寄りをつないでいけるのも芸術家村のおかげだと思っています。90代のおばあちゃんは(柏木)崇吾さんの手(の和紙)も貼ったし、ミシンがけして暗幕も縫ってくれたし。ここがあるからおばあちゃんも元気で張り切ってるのかも」
最盛期には約2000人が暮らしていた粟島も現在の人口は131人。過疎化が進み、人と人との関わりが希薄になりやすい環境だからこそ、アーティストや訪れた人との交流の場を作り続けてきました。
作品は10月3日に始まる瀬戸芸の秋会期で展示されます。制作を終えた柏木さんとサリナさんは10月6日に粟島を旅立ちますが、日々を共にした島の人たちが作品を案内する予定です。
(島民ボランティア/松田悦子さん)
「4カ月一緒に生活したのでそのことを大いにみなさんに言ってあげたい。こんな性格で、こういう意味で、こういう作品ができましたよと、きちんと彼らのメッセージを伝えてあげたい。手は温かいでしょ、太陽のように温かいから植物が育つんだよと」
アーティストと島の人たちの4カ月間の結晶が彩る芸術の秋が、まもなく幕を開けます。
(2025年9月30日放送「News Park KSB」より)